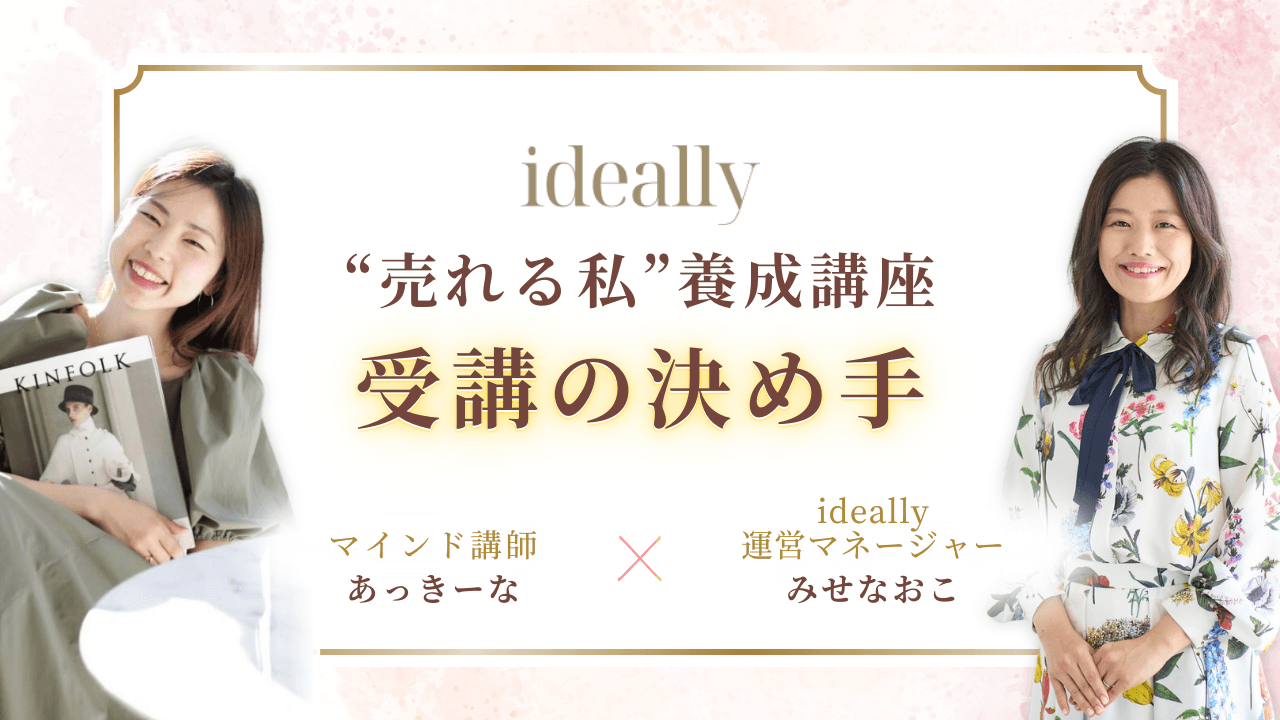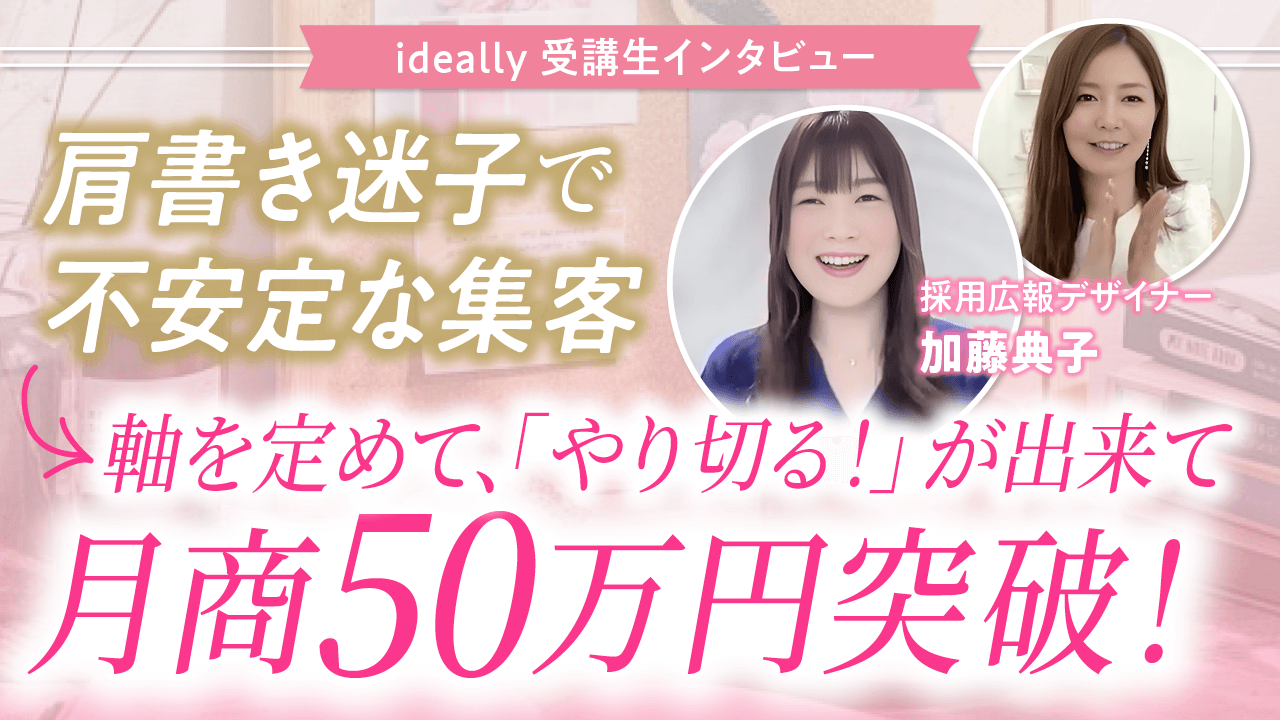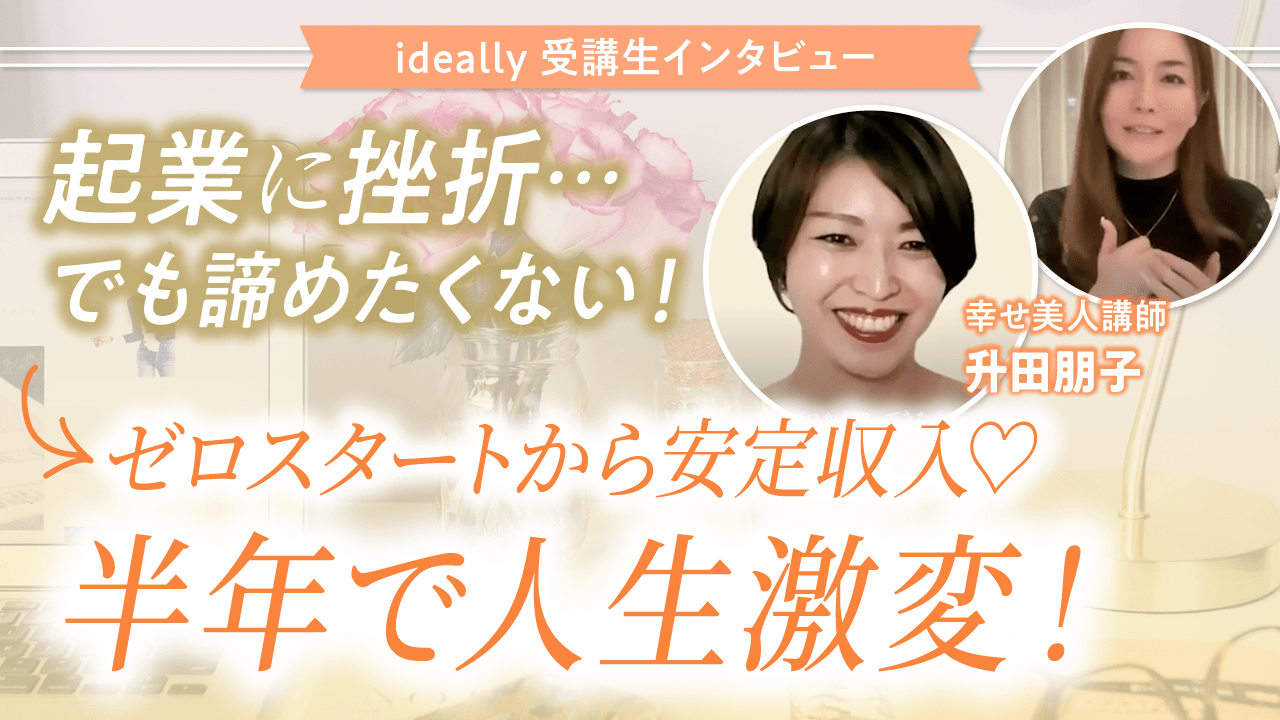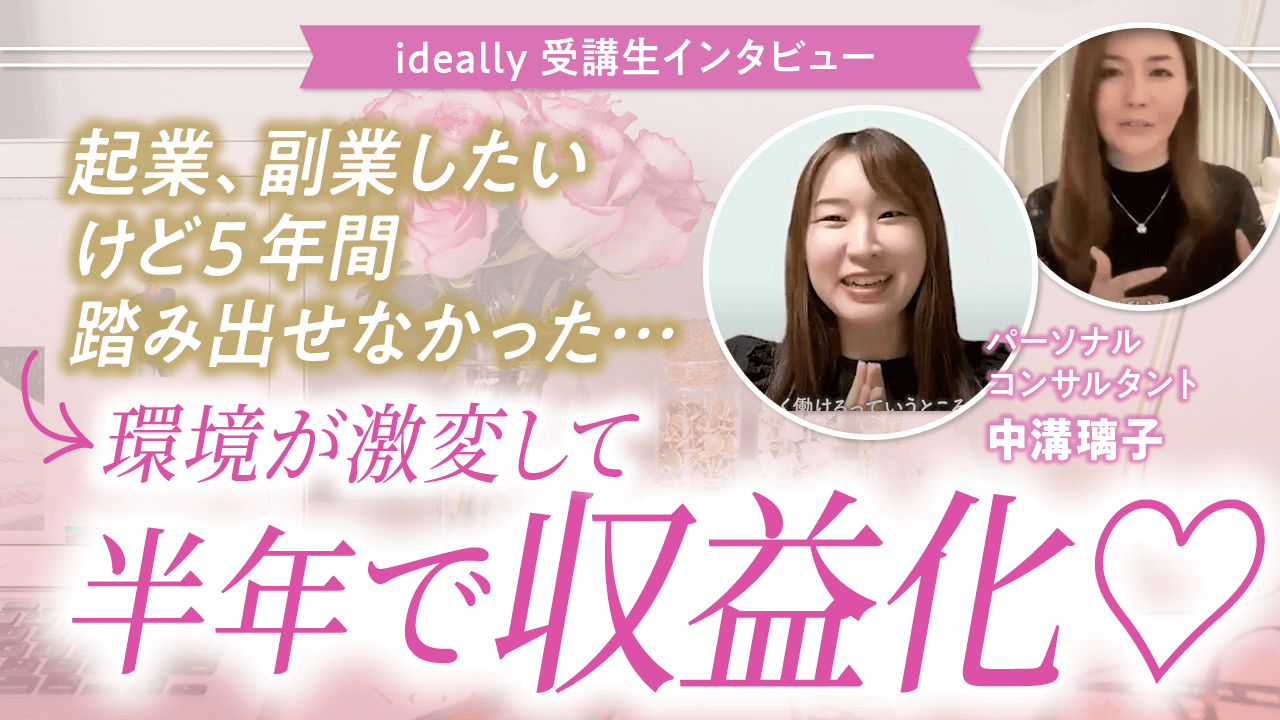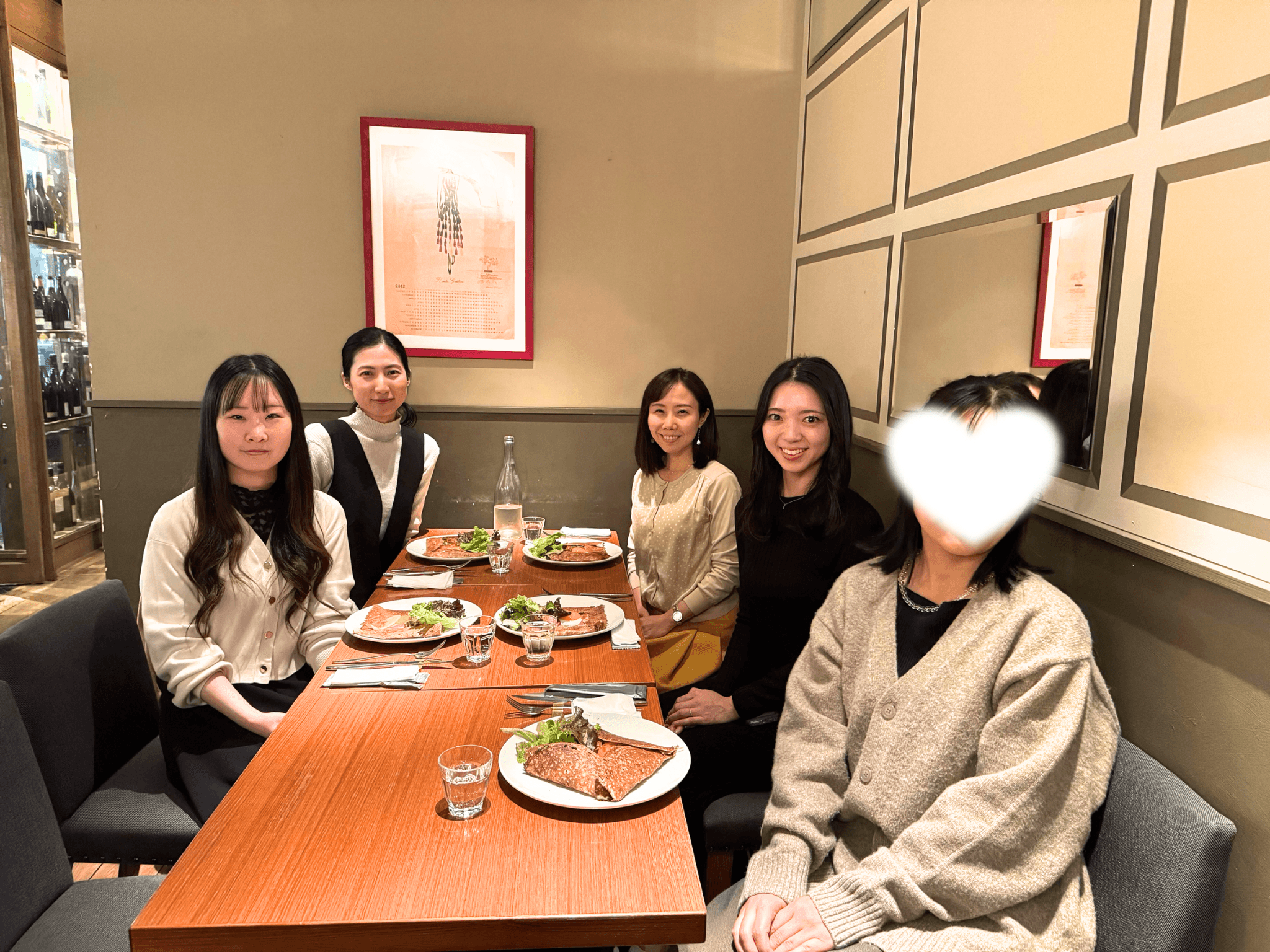2026.02.08
【開催レポ】9/17(水)にパーソナル起業スクールideally主催・東京ランチ会を開催しました!
前回の開催から4ヶ月ぶりにideally東京ランチ会が開催されました!<br> <br> 今回ご参加くださったのは「好きなことを仕事にしたい」と、わくわくの夢に向かって進まれている16名の受講生様。<br> <br> 9月でもまだまだ夏のように暑い日でしたが、表参道エリアのおしゃれなイタリアンレストランに皆様お集まりいただきました。<br> <br> 今回も笑顔やお話が絶えない活気に溢れた会となりました。こちらの記事では、そんなideally東京ランチ会の様子をお届けします。<br> <br> ideallyランチ会とは?<br> <br> パーソナル起業スクールideallyは「心地よく 自由に 私らしく、好きなことを仕事にできる学校」ということで、作家で起業家の宮本佳実さんが校長をされている起業スクールです。<br> <br> <br> 起業をゼロから学べるほか、仲間同士で繋がれるイベント開催がたくさんあるのも受講生の皆様に喜んでいただいている特徴のひとつなのですが、なかでも同じ志を持つ仲間とリアルに会えるランチ会は、毎回とても皆様が楽しみにしてくださっている一推しのイベントなのです。<br> <br> <br> 起業家の交流会というと、いろいろな人が集まるので、<br> <br> <br> 「緊張するな」<br> 「何着ていこう?」<br> 「一人でも大丈夫かな?」<br> 「話せないかも?」<br> <br> <br> と不安になってしまうかもしれませんが、ideallyランチ会は普段はオンラインでしか会えない方達とも会えるので、ぐっと距離が縮まり夢を応援しあえる仲間ができるとご好評をいただいています。<br> <br> <br> 実はideallyランチ会は、お一人参加の方が多数!<br> <br><br> 最初は皆様少し緊張気味の様子ですが、同じように夢に向かって歩まれている皆様なのでお話を始めるとあっという間に意気投合されていらっしゃるなという印象です。<br> <br> 各テーブルに1人、サポートマネージャーも入ってお話をお伺いしますので「自分から話すのが苦手……。」という方も安心です。<br> <br> ランチ会スタート!<br> 受付〜乾杯〜自己紹介<br> 入口で受付したあと、ご自身のお名前の名札が置いてあるテーブルに着席。<br> <br> あらかじめお席もランダムに決めてありますので「どこに座ろう……」「一人ぼっちになっちゃった」ということもありませんのでご安心ください♡<br> <br> 白を基調とした明るい雰囲気のイタリアンレストラン。壁に飾ってある絵画やインテリアもおしゃれです♪<br> <br> 全員揃ったところで「今日は素敵な時間を過ごしましょう」の掛け声で乾杯!<br> <br> <br> その後、<br> ・お名前<br> ・お住まいの地域<br> ・どんなお仕事をしているのか・したいのか<br> <br> などの自己紹介を各テーブルでしていただきました。<br> <br> <br> ランチタイム 〜 フリートーク・情報共有<br> <br> おしゃれな前菜が運ばれてきて、いよいよランチ会スタート♪<br> <br><br> <br> 各テーブルで、ご自身のビジネスの話やideallyに入ったきっかけ、どのような夢を叶えたいかなどそれぞれフリートークや情報シェアなどの会話が飛び交います。<br> <br> 理想の未来に向かって進む仲間同士でも、それぞれの好きや得意は全く違います。<br> <br> 会員Aさん:<br> 「私は人と話すことが好きだけど、とにかくパソコン作業や資料をまとめることが苦手なんです。」<br> <br> とお話しくださる方がいれば<br> <br> <br> 会員Bさん:<br> 「えー!毎週のように講座生さんとお話しされているなんてすごすぎます。資料まとめるのなら私はずっとできます。」<br> <br> とお話ししてくださる方もいたり。<br> <br> <br> 自分の当たり前が当たり前ではないんだ!と新しい発見ができる場所でもあります。<br> <br> 他にも、<br> <br> 「ideallyで学ぶなかで、気づかないうちに周りと比べそうになったけれど、サポマネさんと2人3脚で不安を解消できて、焦る必要ないんだなと前向きになれた」<br> <br> というご自身の体験談をお話をしてくださる方や、<br> <br> 「すでにideallyを卒業したけどその後も活動を続けて、3年かけてやりたいことをやれるようになった!」<br> <br> というお話をしてくださった方などなど。<br> <br> 起業家として進まれる皆様のリアルな話をしあえるのもideallyランチ会ならではの貴重な機会ですね。<br> <br> <br> デザートタイム 〜 ワークシェア・SNS交換<br> <br> デザートが運ばれてくると、楽しいランチ会もあっという間に終盤です。<br> <br> <br> おいしいティラミスをいただきました♪<br> デザートタイムは、事前にお配りしたワークのシェアをしたり、お互いにSNSの交換をしたりなどしていただきました。<br> <br> <br> 今回のワークのテーマは「もし1ヶ月、お金も時間も完全に自由だったら、何をしたい?」というもの。<br> <br> <br> 普段はなかなか考えないことだと思うのですが、だからこそ自由に夢を描いて、それをシェアしあえるという時間に、皆様が一番盛り上がる時間です^^<br> <br> 誰かがシェアするたびに、<br> <br> 「素敵〜♡」<br> 「できるできるー!」<br> といった応援が飛び交い、同じテーブルの仲間たちが温かく応援し合う姿がとても印象的でした。<br> <br> 応援してくれる仲間がいるってそれだけで嬉しくて心強いですよね!<br> <br> <br> 締めの挨拶 〜 記念撮影<br> <br> まだまだ話は尽きませんが、楽しい時間はあっという間。 最後に皆様で集まって記念撮影をしました♡<br> <br> <br> 最初は緊張されていた方も、最後にはすっかり打ち解けて皆様の笑顔がとても素敵です。<br> <br> <br> 「また次回は〇〇のイベントで会おうね!」<br> 「インスタのアカウント、フォローするね」<br> <br> <br> などとお声を掛け合われていました。<br> <br> オンラインでいつでも会えるけど、やっぱりリアルで会う喜びと楽しさは一際ですね!<br> <br> <br> あたたかくて優しい世界に触れられるideallyランチ会♡<br> 美味しい食事を囲みながら、お互いを応援し合い、刺激し合える仲間と繋がれる場所。<br> <br> <br> ideallyランチ会では今回も素敵な皆様が繋がってくださったなと感じます。<br> 毎回素敵な出会いがあり、とてもかけがいのない時間になってくださっていると思います。<br> <br> <br> ご参加くださった皆様、今回も誠にありがとうございました。<br>